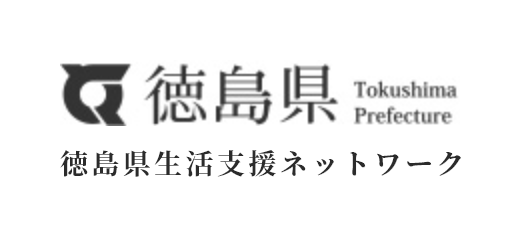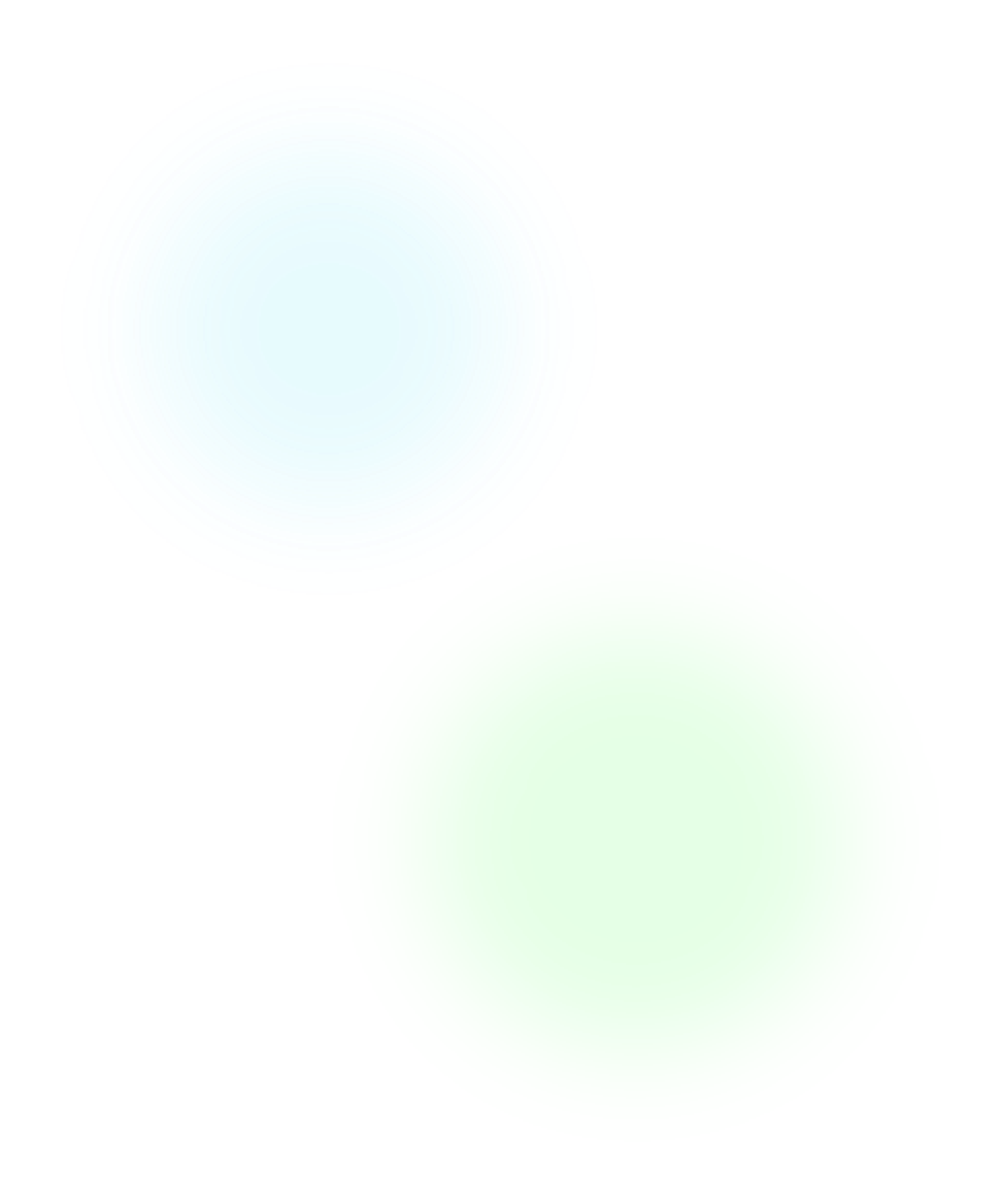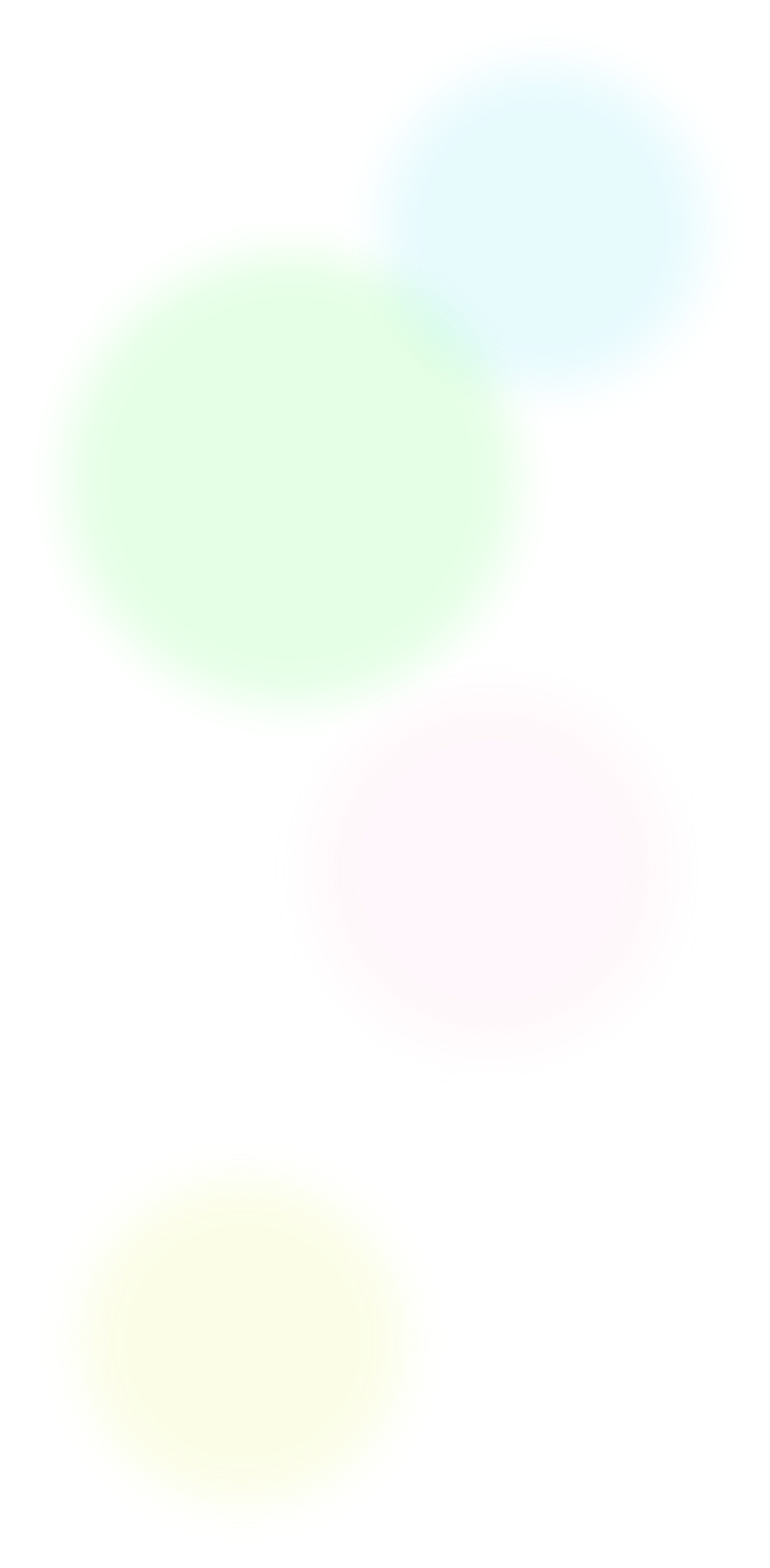支援活動団体一覧
Support Group
徳島県内では、暮らしに困窮されている皆さんを支援するため、民間ボランティアによる「支援活動団体」が組織され、様々な支援活動に取り組まれています。県にご登録いただいた「支援活動団体」についてご紹介いたします。
ご登録を希望される団体の方は以下のフォームよりお申込みください。
支援活動団体一覧
Support Group
検索結果
孤独孤立対策
地域に根付いたどなたでも参加できる食堂です。季節の行事も地域団体と協力して行っています。大勢で食べる楽しさとそこに安らぎがある温かい食堂を目指しています。
食育にも力を入れており、旬のお野菜がたくさん並ぶ食堂です。
キワニスクラブは1915(大正4)年1月21日、米国ミシガン州デトロイト市で設立されました。ロータリークラブやライオンズクラブに並ぶ「世界三大奉仕団体」のひとつで、自分の地域を良くしようとする人々の集まりです。
現在90ヶ国に約8000クラブがあり、会員約26万人が国際キワニスを構成しています。また青少年等を構成員とするサークルKやキークラブ等の「Kファミリー」の会員も合わせると約60万人に上る大きな組織で、キワニスクラブの本部は米国インディアナポリスにあります。
キワニスは社会奉仕活動を行う組織であり、社交団体でも、政治団体でもありません。
徳島キワニスクラブは、2016年12月9日に全国で37番目のクラブとして発足いたしました。世界のキワニアンと心を同じくし、キワニスの目的である「人生の物質的価値より、むしろ人道的、精神的な価値を重くみる」この精神をもとに、未来を担う子ども達を支援するために、徳島キワニスクラブらしい活動を会員一同ともに考え行動してまいります。
・月1回開催・第4木曜日・80歳以上・2時間開催
・在宅高齢者の方への外部とのつながり
・デイサービスに行きたくないが、おしゃべりしたい人のつどいの場
・安否確認、見守り
・孤独感解消
・認知症予防
を目的とした団体です

東高房わっしょい広場」は、就学前の子どもとその保護者を対象に、月1回開催している地域の交流拠点です。
簡単なおもちゃ作りやゲーム、季節行事を通して、親子で楽しい時間を過ごしながら、自然に人と人がつながることを目的としています。
活動当日は、子育てに関する情報交換のほか、手づくりの温かい食卓の時間も設け、参加者同士がゆったりと交流できる雰囲気を大切にしています。
「はじめてでも参加しやすい」「誰でもあたたかく迎えてもらえる」そんな空気づくりを心がけています。
活動の特徴
・月1回(第4月曜日)開催
・就学前の親子を対象(町内外問わず参加可能)
・参加費無料
・事前予約制・定員あり
・申込専用電話 080-8881-8032
・季節行事や創作遊び、交流を中心とした内容

毎週火曜日にいきいき百歳体操、サロンを開催しています。100歳を越えても参加してくれる方がいたり、ほとんどの方が毎回参加して下さっている。筋力トレやボッチャなどを楽しんで取り組んでいる様子を見ると、お世話する側も元気をもらっています。

あすなろこども食堂は、「みんなでごはん、みんなで笑顔!」を合言葉に、地域の子どもや大人が集う温かい居場所です。
地元の方や企業、学生ボランティアの協力で運営し、寄付食材や地元の家庭菜園で収穫された新鮮なお野菜などをつかって手づくりごはんを囲みながら、世代をこえて交流しています。
食をきっかけに、つながり・学び・支えあいが広がる。
あすなろこども食堂は、そんな“まちの笑顔の応援隊”です☆彡
【開催日時】毎月第3土曜日 12:00~13:30
【場 所】北島町江尻防災施設(板野郡北島町江尻字宮ノ元32)
焼肉勝利さん裏側
お手伝いさんも随時募集してます!気軽に遊びにきてね♪

ぎおんさん会は、高齢者の孤独や孤立の解消を目的に、地域のつながりづくりを進めている団体です。外食ランチ会の企画や畑クラブ、体操教室への参加促進、ゲーム大会など、多様な催しを工夫しながら実施し、参加しやすい環境づくりに取り組んでいます。こうした活動を通して、地域住民が気軽に立ち寄れる近所の居場所としての役割を果たしています。
開催地:東高房老人憩いの家 北島町高房字東中道10-1
対象者:北島町東高房にお住いの方
問合せ:osamu.a1005@gmail.com

男性介護者だけではありませんが、介護をする者が会し、介護でのいろいろな困難なことを話題にして、少しでも介護が楽になるよう「愚痴」を言い「仲間」を見つけて情報を入手する場を目指しています。
ご関心がある方は、どなたでもご参加いただけます。参加される場合は、できるだけ事前にご連絡ください。

地域住民を中心に、孤独に悩んだり、孤立したり、災害時に取り残されたりしないために、地域住民に呼びかけ、さらには友人知人に呼びかけ、目佐厚生福祉解放センターにみんなで集まります。そして「生き生き百歳体操」「や脳トレーニング」で健康寿命をのばしています。
また、文化教養講座として絵手紙・一閑張・ペン習字・フラワーアレンジメントを開催し、様々な文化・芸術を学び、心を豊かにするように努めています。そして作品を年数回小松島市役所やサウンドハウスホール等で展示する活動もしています。
脳トレーニング 第2・4金曜日 13:00~15:00
生き生き百歳体操 毎週木曜日 10:00~11:00
絵手紙・一閑張 第2、第4月曜日 13:00~15:00
ペン習字 第2、第4火曜日 13:00~15:00
フラワーアレンジメント教室 第1金曜日 10:00~12:00

「食を通じて地域とつながりたい」——そんな思いから、お弁当配達や地域のお惣菜づくりをしている はれいろキッチン だけでなく、居場所づくりや子ども食堂を運営する活動として はれいろプラス が広がりました。
はれいろプラスでは、子どもたちやそのご家族、高齢の方など、世代をこえて安心して集まれる「ひろば」をつくっています。ごはんを食べるだけでなく、一緒に準備や片付けをしたり、遊びや体験を楽しんだりすることで、子どもたちにとって「ただ食べる場所」ではなく、安心できる学びの場・つながりの場となるように工夫しています。
地域のボランティアさんや住民の方、企業や農家さんからいただいた食材や協力を活かしながら、活動は少しずつ広がっています。冷やしうどんやかき氷のふるまい、ボランティアと一緒に作る焼きそば、農家さんの野菜を使った献立など、季節や人との出会いに合わせて毎回ちがう「食と交流の場」が生まれています。
私たちの思いは、ひとりでも多くの子どもが「ひとりじゃない」と感じられること。経済的・社会的に困難を抱えていても安心して参加できる場所であること。そして、地域全体が「子どもを真ん中に」して支え合えるコミュニティを育てていくことです。
これからも、はれいろプラスは「食べる・学ぶ・遊ぶ・つながる」を大切にしながら、地域の皆さんと一緒に子どもたちの未来を支えていきたいと思っています。

支援活動団体を探す
Search